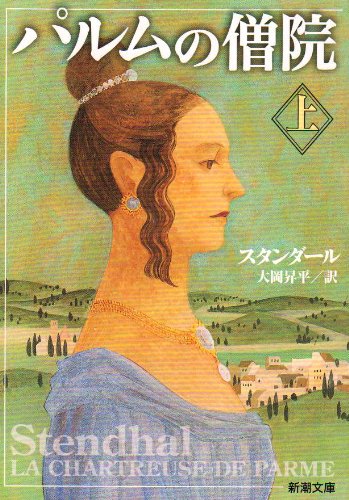
新潮社 新潮文庫 翻訳:大岡昇平 定価:514円=税別
上巻 1951年2月15日発行 63刷改版:2005年4月15日 65刷:2009年2月10日
フランス原語版発行:1839年
われわれが書いたり読んだりしているスポーツノンフィクションのスタイルは何を源流とし、どのような過程を経て現在の形態に至ったのか。
別にそのようなことを気にしなくとも作品を書いたり読んだりすることは可能だが、一応物書きを生業としている以上、やはり知らないよりは知っておいたほうがいいだろうと思い、折を見てある程度系統的な読書を続けている。
ぼくの場合、なるほど、ノンフィクションはこのように書けばいいのか、これに倣えば何とか一冊書けそうだ、と気づかせてくれたのは、30代後半で読んだ大岡昇平の『俘虜記』(1949年)だった。
では、大岡という作家は『俘虜記』を完成させるのに必要とした文体や世界観を、いかにして、どのような作品の影響下において獲得したのか。
それはこの小説だと、大岡本人が語っているのが、スタンダールの『パルムの僧院』(1839年)である。
補充兵として太平洋戦争を体験する以前から自らをスタンダリアンと任じていた大岡は、『俘虜記』を上梓したのちに『パルムの僧院』の翻訳も出版し、現在ではこの大岡版(新潮文庫)が最もポピュラーな日本語版となっている。
あとがきによれば、この訳出が『レイテ戦記』(1971年)の発表より2年前の1969年夏のことで、そう思って読んでいたからか、『パルムの僧院』の全体的な構成に『レイテ戦記』との類似が感じられる部分があちこちに散見される。
また、パルム公国における貴族の群像を面白おかしく描写した部分には、『俘虜記』とよく似た言い回しも見受けられた。
主人公のファブリスはイタリア貴族の次男で、ナポレオンに憧れて戦場に身を投じたロマンチストである半面、自らの美貌で次から次へと女性を籠絡するイケメンの女たらしでもある。
叔母の公爵夫人ジーナはこのファブリスにぞっこんとなり、パルムの宮廷で出世させようと目論むが、ファブリスは恋の鞘当てから旅芸人の役者を殺し、逮捕されて死刑判決を待つ身となってしまう。
一方的に恋している甥を救うため、ジーナは自らの政治力を利用してファブリスを脱獄させようとする。
ところが、ファブリスのほうは自分を投獄した将軍の娘クレリアに恋してしまい、彼女のそばを離れたくないからと、ジーナの救いの手を拒否。
自分が望まなくとも女に不自由したことのなかったファブリスは、恋という感情を知らず、ひとりの女に身も心も捧げるほど惚れ抜いたことがなかった。
ところが、皮肉にも自分が囚われの身となって初めて、どれほど望んでも決して手の届かぬ美少女に熱烈な恋をしてしまったのだ。
当然のことながら、ファブリスの心中を知った公爵夫人は激しい嫉妬の炎に身を焦がす。
果たして、この抜き差しならない三角関係がどのような大団円を迎えるのか。
3人を取り巻く大公やクレリアの父との関係、宮廷で暗躍する身分の卑しい法官ラシ、ジーナに求婚する実力者モスカ伯爵の思惑も相俟って、最後の最後まで目が離せない。
と、こう書くと面白いようだが、現代の小説やノンフィクションばかりを読み慣れた読者は結構何度もつっかえるだろう。
本作が出版されたのはロマン主義文学が全盛を誇っていた19世紀半ばの1839年であり、いま読むとまるで歴史書のような説明文、日本でいえば講談調を思わせる長台詞が作品の大半を占めている。
そこに現在のリアリズム文学にも通じる生々しい戦場の場面が挟まり、その鮮やかな描写が読んでいるこちらをハッとさせるのだが、残念ながらそういうくだりはすぐに終わってしまい、すぐにまた冗長としか言いようのない文章が延々と続く。
しかも、この時代の文学作品の常として、一つの段落の中で目まぐるしく場面が変わり、時制が進行するため、うっかりしているとこれはいつ、どこのお話で、何が問題になっているのか、わからなくなってしまいかねない。
その上、作者のスタンダールが「この話はここですべてを紹介せず読者の想像に任せる」などと、面倒臭かったのか、あるいは創作上の企みでもあったのか、とんでもない省略を挟んで話を飛ばしたりする。
これは本作がスタンダールの口述筆記で、53日間という驚嘆すべき速さで書き上げられたことにも一因があると思う。
歴史的名作に対して恐れげなく言わせてもらえば、もう少しじっくり推敲を重ねるべきではなかったか、と感じさせられた部分も少なくない。
ファブリスとクレリアが結ばれるのか結ばれないのか、散々気を持たせたあげくのクライマックスには、現代では到底納得できないと感じる読者も多いはずだ。
また、ここまで艶やかな絵巻物的メロドラマを繰り広げてきた登場人物たちが、いやにあっさりした説明文によって退場してしまう結末もあまりに食い足りない。
ただし、繰り返しになるが、スタンダールが本作を執筆(正しくは前述のように口述だが)していたとき、文学の世はロマン派全盛であり、リアリズムによる書き方自体がまだ生まれていなかった。
リアリズムはスタンダールの本作によって初めて世に現れ、フランスではギュスターブ・フローベールやエミール・ゾラ、さらにロシアにおいてはレフ・トルストイやフョードル・ドストエフスキーに受け継がれ、現代にまで及ぶ文学の主流を為すに至る。
スタンダールの創始したリアリズムの命脈が、フローベールの写実主義、ゾラの自然主義へ昇華され、彼らの作品世界は現代の小説やノンフィクションへ一気に近づき、いまなお注釈なしで読めるほどの現代文学として成立するようになる。
ノンフィクションの源流はここ、パルムの僧院にあるのだ。
旧サイト:2016年01月4日(月)付Pick-up記事を再録、修正
😁😭😳🤔🤓😖
面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 怖かった😱 考えさせられた🤔 勉強になった🤓 ほっこりした☺️ 癒された😌 腹が立った😠 微妙だった😥 しんどかった😖 ガッカリした😞
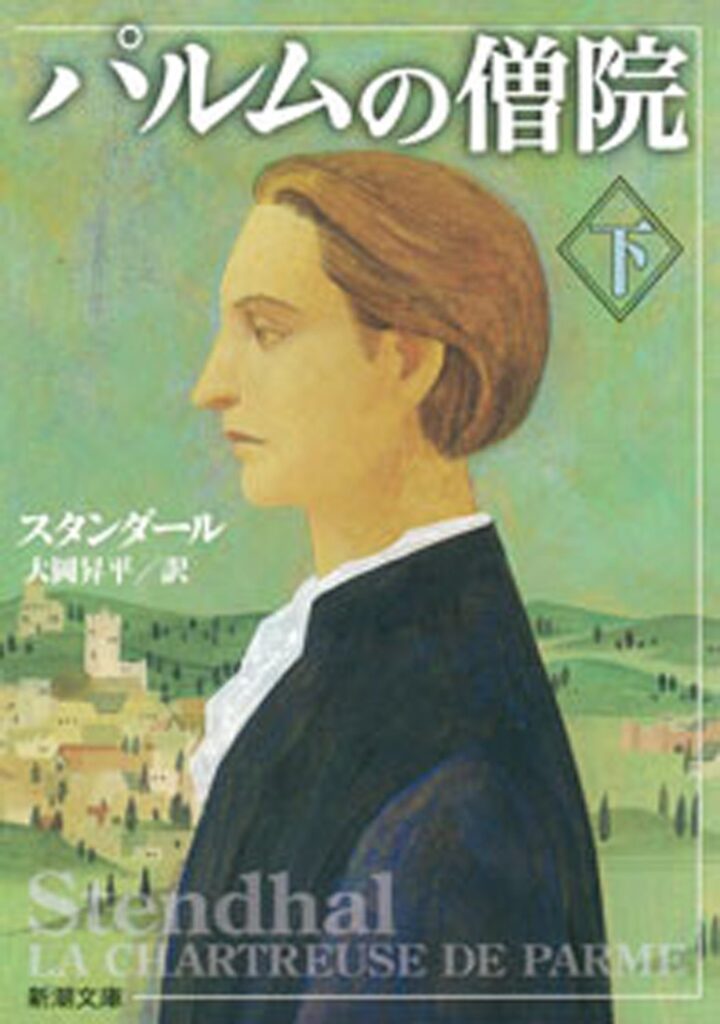
1951年3月25日発行 58刷改版:2005年7月20日 59刷:2007年6月25日


