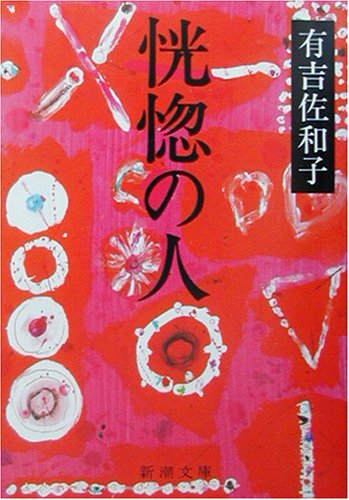
1刷:1982年5月25日 52刷改版:2003年2月25日 70刷:2021年1月10日
単行本発行:新潮社 1972年6月
最近になってこういう本を読んだ理由を率直に打ち明けると、自分もそろそろ、親の介護について考えておかなければならなくなっているからである。
親の老化の程度はこの小説に登場する老人とは随分異なり、うちはまだ軽くてよかったと安堵した一方で、しかしいずれはこうなるのだろうかと想像し、慄然とさせられもした。
時代は全国で核家族が増えつつあった高度経済成長期の1970年代。
東京都杉並区に舅・姑との二世代家屋で、ひとり息子をもうけ、共働きの収入で日々の生活を切り盛りしている主婦の立花昭子が主人公である。
昭子が立花家に嫁いでから何かと文句をつけていた意地悪な舅の茂造が、妻に先立たれてから間もなく、84歳で認知症になった。
以前は昭子のやることなすことに何かと文句をつけていたのに、ボケてしまうと二言目には「昭子さん、昭子さん」と繰り返して嫁に頼り切りになり、なぜか実の息子である信利には見向きもしない。
姑の死後、同じ敷地内の離れで暮らしていた茂造は、やがて近所を徘徊したり、夜中に失禁したりするようになる。
信利は毎日の仕事の忙しさを言い訳にして、そんな実の父親の面倒をまったく見ようとせず、介護を昭子に任せきりにしてしまう。
茂造を離れに置いておけなくなった昭子は、やむなく本宅の別室に茂造を寝かせ、自分も隣に寝て夜中の徘徊に備えることにする。
予想通り茂造が深夜に起き出すと、庭で用を足そうにも自分で陰茎を出せない茂造のため、昭子が逸物に手を添えて小便をさせてやらなければならない。
そんな昭子に協力しながらも、受験生の息子・敏はどこか冷めた態度で、自分が大人になったとき、お父さんやお母さんはおじいさんのようにならないでね、と昭子と信利に向かって言う。
弁護士事務所に勤めている昭子は過労と寝不足が重なり、このままでは昭子のほうが倒れてしまうのではないかと、これはフィクションだとわかってはいても、読み進めながらハラハラさせられる。
昭子は茂造を預かってもらえる施設を探して回るが、ここでも認知症の老人が入所するには様々なハードルがあることがわかってくる。
後半からクライマックスに至るくだりは昭子がさらなる下の世話を強いられる描写の連続で、同情を通り越してほとんど恐怖すら覚える。
そんな最中、息子の敏が男性用便器で用を足したとき、勢いよく便器をたたく小便の音を聞いた瞬間、「これが若さだ」と昭子が悟る場面が、なぜか爽やかな、ある種のカタルシスを感じさせる。
読んでいるうちに50年も前の小説であることを完全に忘れてしまって、ようやく辿り着いたラストシーンは超高齢化社会と化した現代を象徴しているかのようにも思えて印象深い。
恐らく、今も日本全国のあちこちの家庭で同じような相克と葛藤が繰り広げられているのだろう。
程度の差こそあれ、僕の家族も、いや僕自身も決して例外ではない。
😁 😭 😢😳 😱 🤔🤓 😌
面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 怖かった😱 考えさせられた🤔 勉強になった🤓 ほっこりした☺️ 癒された😌 腹が立った😠 微妙だった😥 しんどかった😖 ガッカリした😞


