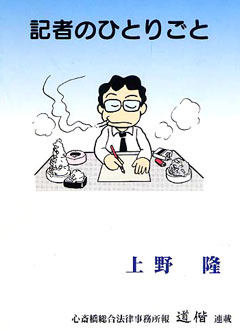
○心斎橋総合法律事務所報『道偕』2003年4月号掲載
近鉄から中日に移籍した大塚晶文投手の胸中に去来するものは何だったのだろうか。
6年前、抑え投手として貢献した右腕は、最後は感情的なしこりを残してセ・リーグへ去っていった。
球団の対応がまずかったのか、意思を貫き通した選手がわがままだったのか。
後味の悪い取材だった。
入札制度(ポスティングシステム)と呼ばれる約束事ができたのは、時代の流れの中で必然的だった。
球団にも選手にも都合のいいルールだった。
それまで日本のプロ野球に属する選手が米大リーグに移籍するにはFA権を得ている必要があった。
しかし、それでは選手によっては30歳代の半ばに達することもある。
「力の発揮できる若いときに大リーグへ行きたい」と選手が願うのは無理もなかった。
入札という言葉で示される通り、大リーグの各球団の中で最も高い金額を提示したところが、その日本選手と契約する権利を得る。
一見、わかりやすいシステムだが、選手側に球団を選べる自由はない。
このあたりが問題になりそうな予感はあった。
今回の大塚のケースはまさにそこに端を発している。
入札した米球団がゼロという事態を、球団も大塚も全く予想していなかった。
近鉄にすれば、入札に失敗した以上は、FA権を得ていない大塚の身分は現所属球団に残る、と見なすのは自然だろう。
しかし、大塚本人はそう考えなかった。
いったん出すことを決めたのだから、結果はどうあれ、身分は近鉄から離れたと考えた。
実際、お別れセレモニーもすませていた。
昨年12月に入札失敗が明らかになってから約3カ月。
「残留せよ」「嫌だ」の応酬が続いた。
不毛の争いだった。
近鉄は大塚の真意を知っているが、認めたくはない。
認めれば選手のわがままに弱い球団だと思われる。
結局、出た答えは時間をかけての中日へのトレードだった。
「説得に努力したのだが、だめだった」と球団は言い訳できた。
大塚も近鉄から逃れられた。
要するに「痛み分け」だった。


