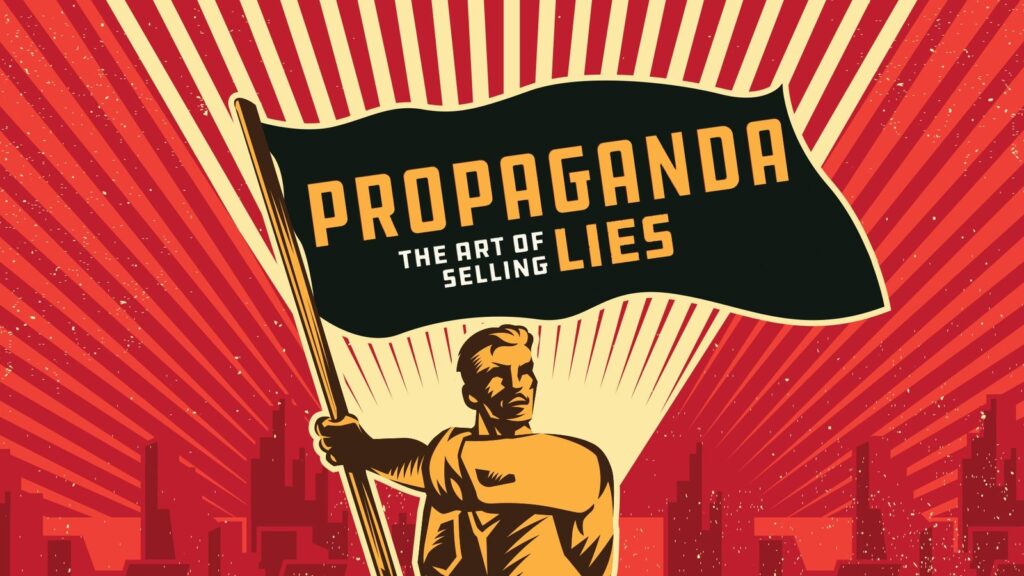
45分(オリジナル版92分) 2019年
制作:カナダ、ドイツ=Hawkeye Pictures/Taglicht Media
初放送:2019年10月30日(水)午前0時00分~
再放送:同年11月6日(水)午後6時00分~
再々放送:2020年5月22日(金)午前0時〜
本作にはプロパガンダに関する様々な警句や金言が引用されている。
冒頭で最も印象に残るのは、「あらゆる芸術はプロパガンダである」というジョージ・オーウェルの言葉だ。
われわれは通常、様々な写真や映像、映画や小説といった娯楽作品や芸術作品を指して、「これはプロパガンダだ」「いや、単なるプロパガンダではない」などと議論する。
しかし、そもそもプロパガンダに当てはまる作品とはどのようなものなのか。
オープニングで矢継ぎ早に様々な映像が紹介されたあと、本作は〝世界最古のプロパガンダ作品〟として、スペインのエル・カスティージョ洞窟の壁画を紹介。
ここに残された絵の数々は、旧石器時代のシャーマン的立場にあった人間が人々を洗脳するため、大変巧妙に描かれている、というのだ。
それぐらい、プロパガンダの歴史は古い。
古代ローマ時代のアレクサンドロス大王は、全国に流通する硬貨に自分の肖像画を刻みつけ、この国の王が自分であるという認識を国民に刷り込むためのツールとして利用した。
印刷技術が発達した16世紀には、マルティン・ルターが文書と木版画による文書を作り、カトリック教会の免罪符を批判するプロパガンダを展開。
キリスト教は20世紀においても、欧米によるアジア圏やイスラム教圏への侵略や戦争を正当化するためのキャンペーンに散々利用されているから、いまさらながらこの説明には腑に落ちるものがあった。
面白いのは、全世界でポスターやTシャツになっているチェ・ゲバラの肖像画にまつわるエピソード。
これはそもそも、1963年にたまたまゲバラと会ったアイルランドの芸術家ジム・フィッツパトリックが、ゲバラの死後に描いたものだった。
ゲバラの熱烈な信奉者だったフィッツパトリックは、肖像画をシンプルなイラストにブラッシュアップし、自らビラにして様々な場所で配布。
自ら著作権を放棄してフリー素材にしたため、ゲバラの政治立場を超え、さらに世界中で世代と性別を凌駕し、様々な人々の間に行き渡ることになった。
ここでは、ついにマラドーナまでが自分の右腕にゲバラのタトゥーを入れ、自慢げに見せびらかしている画像が紹介されている。
この意図せぬプロパガンダ効果に、「東京の公衆トイレでも見かけたことがあるほどで、自分でも正直ビビりましたよ」とフィッツパトリックは言う。
後半で紹介されるのは、ヒトラー、レーニン、毛沢東など、独裁者が映画を使って繰り広げたプロパガンダの数々。
とくに、ヒトラーの要請を受け、好きなだけ多額の予算を注ぎ込み、ナチスの宣伝映画を制作し続けたレニ・リーフェンシュタールが社会と後世に与えた影響は大きい。
代表作『意志の勝利』(1943年)の映像はいま観ても実に見事。
こうした諸作品がナチスの台頭を強力に後押しした半面、影響を受けた映画人が輩出し、撮影、演出、編集の技術の進歩にも大きく貢献したのだった。
そのヒトラーは、「プロパガンダの神髄とは、大衆の感情と思考への理解だ」と言っている。
リーフェンシュタールもこう言われたら、自分は悪魔のような独裁者に加担しているのだとは思わなかったようで、実際、嬉々としてナチスの宣伝映画を制作し、自分の作品をプロパガンダだとは認めようとしなかったと言う。
リーフェンシュタール作品の芸術的側面とプロパガンダとして利用された政治的側面とは両立するのか、いくら芸術作品として優れていても、ユダヤ人の虐殺に利用されたのなら価値などないのではないか。
そういう芸術作品の鑑賞者が抱く共通の疑問に対し、毛沢東は「純粋な芸術など存在しない。芸術はすべて政治的だ」という言葉を残している。
オススメ度A。


