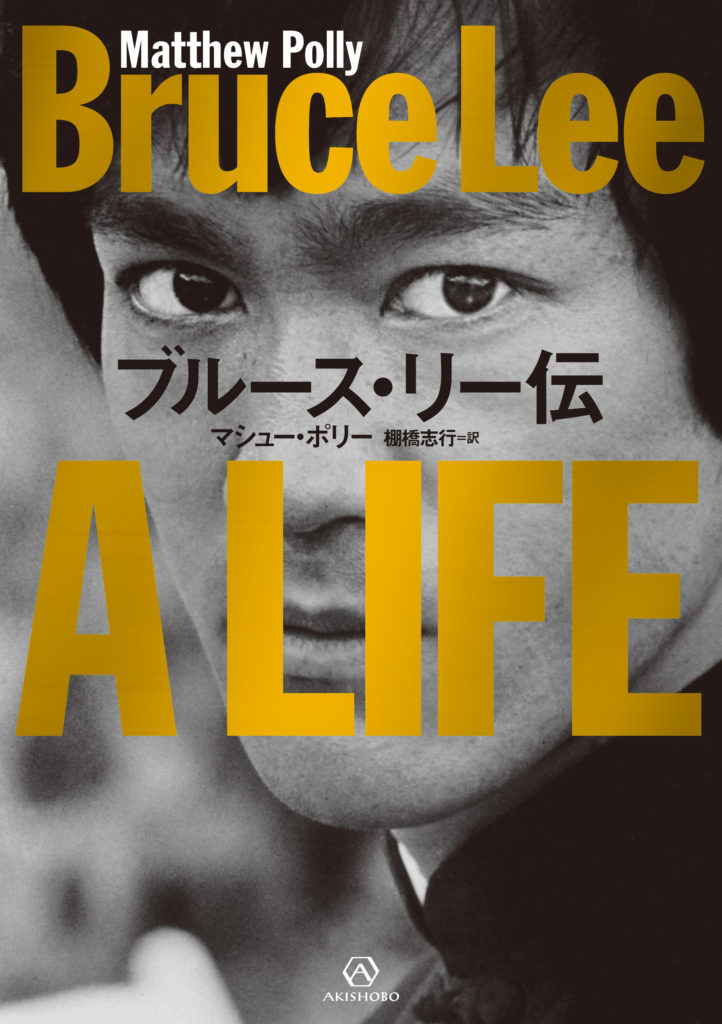
569ページ 亜紀書房 翻訳:棚橋志向 第1刷2019年9月20日 定価5400円=税別
原著発行2018年
来年で生誕80周年を迎えるブルース・リーの決定版的評伝。
発売当日にネット書店で買おうとしたら、約570ページ、上下2段組という今時のネット世代なら寄りつきもしないような分厚さにも関わらず、amazon、楽天、セブンネットショップと軒並み売り切れとなっていた。
それならばと、近所の神楽坂をはじめ、リアル書店を覗いてみたんだけど、やっぱりどこにも置いてない。
本が売れないこの時代、すげえ初速だな、増刷を待つしかなさそうだな。
そう思いながら、里帰りを兼ね、中国新聞とWEDGE Infinityの仕事で広島に出張した先月末のこと。
広島の大型書店ならまだ初版が残ってるんじゃないかと思いつき、丸善に行ってみたら、あったんですよ、辛うじて2冊。
で、読んでみたら予想通り、いや、予想を上回る面白さ!
ブルース・リーの主演映画5本はすべて観ており、リーの人物像に関する基礎的な知識も持っていると自負していたが、こうして改めて時系列に沿って書かれた伝記を読むと、意外に知らなかった事実が非常に多いことに驚かされた。
例えば、リーの父親が俳優で、リー自身も幼少期に子役として香港映画に出演していたことは知っていても、母方の曽祖父がユダヤ系オランダ人で、イギリス人の血も混じっている(いわゆる欧亜人種=ユーラシアン)ことは知らなかった。
さらに、リーは両親が滞在していたロサンゼルスで生まれており、幼くしてアメリカ文化の影響を受けて育つことになる。
また、32歳で夭逝したリーはしばしば「東洋のジェームズ・ディーン」とも言われたが、リー自身、カンフーを自分の売り物にするまでは、ディーンの演技を参考にしていたという。
事実、19歳で不良少年を演じた主演作品『人海孤鴻』(1959年)ではディーンの『理由なき反抗』(1955年)を真似たそうで、この映画は香港で大ヒットした。
若いころはストリート・ギャングのリーダーで、詠春拳の道場に通ってクンフーの技を覚える一方、街中で喧嘩を吹っかけては警察沙汰になり、高校で持て余されたために〝出生地〟のアメリカへ留学。
進取の気性に飛んでいたリーは、昔ながらの形式を重視した中国拳法に飽き足らず、自分流の拳法(のちの截拳道=ジークンドー)を考案し、これをアメリカ人たちに教えて収入を得る。
この時期に知り合い、截拳道を指南した〝弟子兼友人〟に、『ドラゴンへの道』(1972年)や『燃えよドラゴン』(1973年)でリーの敵役を務めたチャック・ノリスやボブ・ウォールがいた。
そして、売れっ子脚本家スターリング・シリファントの知遇を得て、スター俳優のスティーヴ・マックィーンやジェームズ・コバーン、名監督ロマン・ポランスキーの〝師匠〟になる。
こうしてリーは、アメリカでも有名な中国人初の映画スター、それもマックィーン以上の大物になってやる、という野望を抱く。
しかし、この1960〜70年代初頭、アメリカ社会やハリウッドの映画業界における中国人(もしくはアジア人全般)の地位はまだまだ低く、主演どころか、まともなセリフのある役にありつくことすら難しい。
一方、中国古来の拳法の型や思想を否定し、中国人以外の人種に自分の拳法を伝授したリーはやがて、中国や香港の拳法界から裏切り者と見なされるようになってしまう。
ブレークする前のリーは、アメリカと中国という二つの国を股にかけたスターを目指しながら、その両国から敵視されるという極めて特殊な〝アイデンティティー・クライシス〟に陥っていたのだ。
だからか、故郷・香港で『ドラゴン危機一発』(1971年)からようやく主役の座を勝ち取ったリーの自己主張はまことに凄まじい。
相手が監督のロー・ウェイ、プロデューサーのレイモンド・チョウでも容赦せずに罵声を浴びせ、監督も脚本もおれにやらせろ、さもなければおまえらとは絶縁だ、などと平然と言い放つ。
その半面、リーは自分に類い稀な人好きのする魅力、はっきり言えば〝人たらし〟の才能があることも自覚していた。
ウェイやチョウとの交渉が決裂すると、当時の香港映画界をチョウと二分していたライバル、ランラン・ショウに臆面もなくすり寄って、より有利な条件で自分を売り込もうしている。
こういうリー一流の作戦は対マスコミ、対中国拳法界にも発揮され、これ以上角突き合ってはまずい、と察知すると、彼は途端に〝手加減勝負〟や〝微笑み外交〟に切り替える。
強気に出られる相手と状況なら暴力をチラつかせて脅すことも辞さず、取り込んだほうが得だと判断すると魅力的な笑みと機知に富んだ話術で籠絡するのだ。
リーの処世術は、私が1年4カ月付き合い、100時間以上インタビューした俳優・萩原健一にそっくりである。
リーも恐らく、面と向かってインタビューしたら、かつてのショーケンに勝るとも劣らない〝磁力〟の持ち主だったはずだ。
そういうリーの人物像が薄っぺらく感じられないのは、自ら少林寺で2年間修行を積んだという著者が、リーの哲学と人生観を要所要所でしっかり描き込んでいるからこそ。
截拳道の極意を、一定の型に嵌めないこと、そもそも拳法とはそれぞれの個性に合わせた戦いであるべき、だから理想は「水のようであること」という、有名なリーの言葉も、本書を読んで初めて腑に落ちた。
リンダ夫人、娘のシャノン、愛人だったベティ・ティンペイをはじめ、香港映画界のレイモンド・チョウ、ロー・ウェイ、ジミー・ウォング、ハリウッド映画界のフレッド・ワイントローブ、ロバート・クローズ、ジェームズ・コバーン、チャック・ノリス、ジョン・サクソンなどなど、現在インタビューできるリーの主要な関係者はほぼ網羅されている。
32歳での突然死の真相は帯に謳われているほど衝撃的ではなく、新証拠が提示されているわけでもないが、説得力があるのも確か。
しかし、死ぬ寸前のリーは、リンダ夫人や関係者たちも認めているように、明らかに常軌を逸した言動が多い。
著者は断定を避けているが、リーがマリファナやハシシにどれだけ耽溺していたのか、ショーケンのようにコカインには手を出していなかったのか、嚥下できない疑問が残った。
2019読書目録
※は再読、及び旧サイトからのレビュー再録
28『タイムマシンのつくり方』広瀬正(1982年/集英社 集英社文庫)
27『時の門』ロバート・A・ハインライン著、稲葉明雄・他訳(1985年/早川書房 ハヤカワ文庫)
26『輪廻の蛇』ロバート・A・ハインライン著、矢野徹・他訳(2015年/早川書房 ハヤカワ文庫)
25『変身』フランツ・カフカ著、高橋義孝訳(1952年/新潮社)
24『ボール・ファイブ』ジム・バウトン著、帆足実生訳(1979年/恒文社)
23『車椅子のヒーロー あの名俳優クリストファー・リーブが綴る「障害」との闘い』クリストファー・リーブ著、布施由紀子訳(1998年/徳間書店)
22『ベストセラー伝説』本橋信宏(2019年/新潮社 新潮新書)
21『ドン・キホーテ軍団』阿部牧郎(1983年/毎日新聞社)※
20『焦土の野球連盟』阿部牧郎(1987年/扶桑社)※
19『失われた球譜』阿部牧郎(1998年/文藝春秋)※
18『南海・島本講平の詩』(1971年/中央公論社)※
17『カムバック!』テリー・プルート著、廣木明子訳(1990年/東京書籍)※
16『ボール・フォア 大リーグ・衝撃の内幕』ジム・バウトン著、帆足実生訳(1978年/恒文社)※
15『ショーケン 最終章』萩原健一(2019年/講談社)
14『頼むから静かにしてくれ Ⅱ』レイモンド・カーヴァー著、村上春樹訳(2006年/中央公論新社)
13『頼むから静かにしてくれ Ⅰ』レイモンド・カーヴァー著、村上春樹訳(2006年/中央公論新社)
12『試合 ボクシング小説集』ジャック・ロンドン著、辻井栄滋訳(1987年/社会思想社 教養文庫)
11『ファースト・マン 月に初めて降り立った男、ニール・アームストロングの人生』ジェイムズ・R・ハンセン著、日暮雅通・水谷淳訳(2019年/河出文庫)
10『平成野球30年の30人』石田雄太(2019年/文藝春秋)
9『toritter とりったー』とり・みき(2011年/徳間書店)
8『Twitter社会論 新たなリアルタイム・ウェブの潮流』津田大介(2009年/洋泉社)
7『極夜行』角幡唯介(2018年/文藝春秋)
6『力がなければ頭を使え 広商野球74の法則』迫田穆成、田尻賢誉(2018年/ベースボール・マガジン社)
5『OPEN アンドレ・アガシの自叙伝』アンドレ・アガシ著、川口由紀子訳(2012年/ベースボール・マガジン社)
4『桜の園・三人姉妹』アントン・チェーホフ著、神西清訳(1967年/新潮文庫)
3『かもめ・ワーニャ伯父さん』アントン・チェーホフ著、神西清訳(1967年/新潮文庫)
2『恋しくて』リチャード・フォード他、村上春樹編訳(2016年/中公文庫)
1『月曜日は最悪だとみんなは言うけれど』ティム・オブライエン他著、村上春樹編訳(2006年/中央公論新社)


