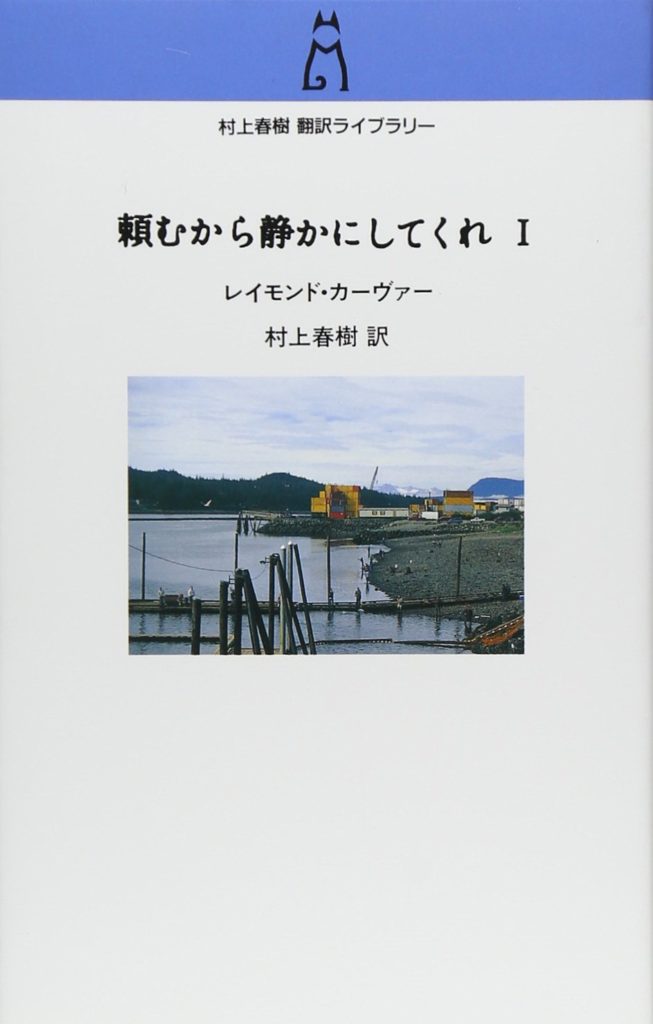
初版発行:2006年1月10日 5刷発行:同年8月25日)
レイモンド・カーヴァーという作家に初めて興味を抱いたのは、2015年のアカデミー作品賞など主要4部門を受賞した映画『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』を観たときである。
マイケル・キートン演じる主人公は若いころ、カーヴァーに演技を褒められたことがきっかけで俳優を志し、年老いて仕事にあぶれているいま、カーヴァーの短編を舞台化してもう一花咲かせようとしている。
その後、いつか読んでみようと思いながらしばらく忘れていたのだが、同じ中公の新書シリーズ〈村上春樹 翻訳ライブラリー〉所収の『月曜日は最悪だとみんなは言うけれど』を読んだとき、この作家は今度こそちゃんと読まなければならない、と認識を新たにした。
ここに掲載された『誰がレイモンド・カーヴァーの小説を書いたのか?』を読み、代表作とされる名短編の数々が編集者ゴードン・リッシュとの〝共作〟、もしくは妻テス・ギャラガーの作品の〝剽窃〟という疑いがあることを知り、俄然興味が沸いたのだ。
言ってみれば、大作家についての暴露本を読んでからその作家の作品を読んだようなもので、あまり褒められたアプローチではない。
ただ、読んでいる間は、これらの諸作がいわゆる盗作であるかどうかはあまり気にならなかった。
一番印象に残ったのは、最初から2番目に収録されている『隣人』(1971年)である。
主人公は当時のアメリカ社会で可もなく不可もなし、世間並みの幸せな生活を送っているビルとアーリーンの夫婦。
彼らがそれなりに満ち足りた生活を送っていた最中、アパートの向かいの部屋に住むストーン夫妻から、しばらく旅行に出ている間、猫と植木の世話をするよう頼まれ、鍵を預かる。
最初は猫と植木の世話だけをしていたビルとアーリーンはやがて、ストーン家のウイスキーを飲んだり、お洒落なドレスを着たり、冷蔵庫の中の高価な食物を漁ったりする。
帰ってきたストーン夫妻にバレたらどうするのかと恐れ始めたアーリーンを、ビルが「大丈夫だ」と言って抱き締め、唐突に終わる。
下手なオチがつくより、よっぽど不安を掻き立てられる幕切れだ。
ちなみに、〝共作疑惑〟を暴かれたリッシュが〈エスクァイア〉への掲載を決断し、カーヴァーを高級商業誌の作家に押し上げることに成功したのが本作。
ただし、そうした裏話をあらかじめ知っていても、作品それ自体は独立した完成度の高さを示している、と感じる。
『サマー・スティールヘッド(夏にじます)』(1973年)は、リチャード・フォードの短編と言ってもおかしくないような子供の世界が描かれている。
性に目覚め始めたばかりの少年がバーチ・クリークに出かけ、偶然出会った少年とふたりで大きなにじますを釣り、二つに切って頭のほうを家に持ち帰る。
ところが、父親は「そんなものを家に持ってくるな」と一喝。
誰の記憶にもある少年期のトラウマを思い起こさせ、酸っぱさとともに生臭さを感じさせる。
『父親』(1960年)の最後の1行の切れ味と不気味さ、『学生の妻』(1964年)で幼妻が抱く不安、『そいつらはお前の亭主じゃない』(1972年)のくたびれた亭主の惨めさと情けなさも忘れがたい。
しかし、おれが似たような短編小説を書いても、誰も評価してくれないだろうなあ。
2019読書目録
12『試合 ボクシング小説集』ジャック・ロンドン著、辻井栄滋訳(1987年/社会思想社 教養文庫)
11『ファースト・マン 初めて月に降り立った男、ニール・アームストロングの人生』ジェイムズ・R・ハンセン著、日暮雅通・水谷淳訳(2019年/河出文庫)
10『平成野球30年の30人』石田雄太(2019年/文藝春秋)
9『toritter とりったー』とり・みき(2011年/徳間書店)
8『Twitter社会論 新たなリアルタイム・ウェブの潮流』津田大介(2009年/洋泉社)
7『極夜行』角幡唯介(2018年/文藝春秋)
6『力がなければ頭を使え 広商野球74の法則』迫田穆成、田尻賢誉(2018年/ベースボール・マガジン社)
5『OPEN アンドレ・アガシの自叙伝』アンドレ・アガシ著、川口由紀子訳(2012年/ベースボール・マガジン社)
4『桜の園・三人姉妹』アントン・チェーホフ著、神西清訳(1967年/新潮文庫)
3『かもめ・ワーニャ伯父さん』アントン・チェーホフ著、神西清訳(1967年/新潮文庫)
2『恋しくて』リチャード・フォード他、村上春樹編訳(2016年/中公文庫)
1『月曜日は最悪だとみんなは言うけれど』ティム・オブライエン他著、村上春樹編訳(2006年/中央公論新社)


