Дущечка / Дама с Соб ачкой
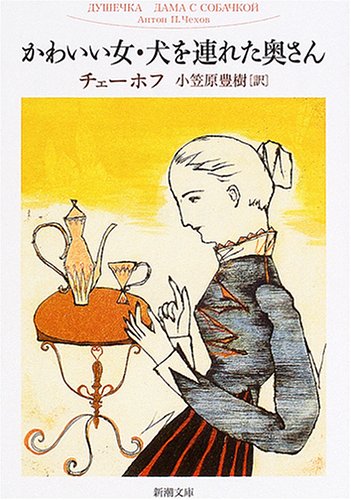
1904年に44歳という若さで早逝したチェーホフは、37歳だった1897年、結核の発作を起こして激しい喀血に襲われた。
以後、迫りくる死を現実の恐怖として受け止めながら、亡くなる前年の1903年に書き上げた最後の短編が、本書の巻末に収められた『いいなずけ』である。
主人公はロシアの辺鄙な土地で暮らす23歳の娘ナージャ。
アンドレイという婚約者がいるのだが、挙式が近づくにつれ、この結婚に疑問を感じるようになっている。
アンドレイは好感の持てる青年で、かつては確かに愛していたが、定職を持っておらず、一緒になったら貧しく退屈な田舎暮らしをするほかない。
そんな未来を夢想してナージャが暗澹たる気持ちになっているところへ、遠い親戚にあたる没落貴族の末裔、サーシャという無名の芸術家が療養にやってくる。
いつまでもこんなところに引っ込んでいては駄目だ、モスクワかペテルブルグに行って自分の人生を切り拓くべきだとサーシャに説かれ、ナージャは家族も婚約者も捨てて家を出る。
その数カ月後、郷愁に駆られたナージャはいったん家に帰ってくるが、その矢先、サーシャが死んだという知らせが届き、ふたたび故郷を去る決心をする。
最初にこの短編を読んだときは、正直なところ、単にマリッジブルーに陥った娘を淡々と描写したような作品という印象しか受けなかった。
が、その後、チェーホフがもっと若いころに書き、自分の死生観を反映させた『敵』(1887年)や『黒衣の僧』(1894年)を読んで、もう一度この『いいなずけ』を再読し、ようやく本作の本質が見えてきた(ような気がする)。
サーシャはすでに死期を悟っていたチェーホフの分身で、ナージャはチェーホフが未来への希望を託したロシアの若者たちの象徴として捉えることができる。
いつでも自分を迎え入れてくれる家族は温かく、田舎も住むには心地よいところだが、いつまでもそこにいては本当の自分の人生へと歩み出すことはできない。
チェーホフは人の優しさや家族の愛情を柔らかな筆致で描きながら、しかしそれは決して人生の成功や幸福を約束するものではなく、人間は結局、ひとりで歩いていかなければならないのだと、淡々と諭しているかのように感じられる。
そうしたチェーホフの悟りの境地が最もよく示されているのが、結核を発症してから1年後に書かれた『かわいい女』(1899年)だろう。
この作品の主人公オーレンカは、舞台演出家と結婚していた間は生活のすべてを芝居に捧げていた。
が、その夫と死別して材木商と一緒になると、今度は林業こそ国家と世界を支えている立派な仕事だと思い込み、「芝居なんてつまらぬ暇つぶし」だと言って一顧だにしなくなる。
ところが、その材木商とも死に別れて、軍隊とともに町へやってきた獣医を新たな恋人にしたオーレンカは、今度は動物を可愛がることしか考えられなくなる。
しかし、その獣医が軍隊とともに去ったあと、彼女は「自分」というものがないことに初めて気がつくのだ。
「何よりも始末が悪かったのは、自分の意見というものが全くなくなってしまったことだった。
周囲のさまざまな対象を目では眺め、あたりで起ることをすべて理解はするのだが、何事についても意見をまとめることができず、何を話したらいいか分からないのである。
ところで、なんの意見も持たぬということは、なんと恐ろしいことだろう!
(亡くなった夫たち)クーキンやプストワーロフが生きていた頃なら、あるいは獣医と一緒だった頃なら、オーレンカはすべてを説明できたし、どんなことについても自分の意見を述べることができたが、今では頭脳の中も、心の中も、中庭と同じようにがらんとしてしまった」
ここには、他者による愛情、他者との関係性の中にしか生きがいや生きる目的を見出し得なかった人間存在の哀しさ、虚しさが見事に表現されている。
人間とはしょせんそういう生き物にすぎないのかもしれない、という諦念も含めて。
(発行:新潮社 新潮文庫 翻訳:小笠原豊樹
1刷:1975月11月30日 45刷改版:2005年2月15日 51刷:2015年3月20日 定価:490円=税別
原著刊行:1896~1904年)
2018読書目録
20『カラマーゾフの兄弟』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳(初出1880年/新潮社)
19『マリア・シャラポワ自伝』マリア・シャラポワ著、金井真弓訳(2018年/文藝春秋)
18『スポーツライター』リチャード・フォード (1987年/Switch所収)
17『激ペンです 泣いて笑って2017試合』白取晋(1993年/報知新聞社)
16『激ペンだ! オレは史上最狂の巨人ファン』白取晋(1984年/経済往来社)
15『戦国と宗教』神田千里(2016年/岩波書店)
14『陰謀の日本中世史』呉座勇一(2018年/KADOKAWA)
13『無冠の男 松方弘樹伝』松方弘樹、伊藤彰彦(2015年/講談社)
12『狐狼の血』柚月裕子(2015年/KADOKAWA)
11『流』東山彰良(2015年/講談社)
10『炎と怒り トランプ政権の内幕』フランク・ウォルフ著、関根光宏・藤田美菜子他10人訳(2018年/早川書房)
9『カシタンカ・ねむい 他七篇』アントン・チェーホフ著、神西清訳(初出1887年~/岩波書店)
8『子どもたち・曠野 他十篇』アントン・チェーホフ著、松下裕訳(初出1888年~/岩波書店)
7『六号病棟・退屈な話 他五編』アントン・チェーホフ著、松下裕訳(初出1889年~/岩波書店)
6『最強軍団の崩壊』阿部牧郎(1980年/双葉社)
5『女子プロレスラー小畑千代 闘う女の戦後史』秋山訓子(2017年/岩波書店)
4『白鵬伝』朝田武蔵(2018年/文藝春秋)
3『ザナック/ハリウッド最後のタイクーン』レナード・モズレー著、金井美南子訳(1986年/早川書房)
2『テトリス・エフェクト 世界を惑わせたゲーム』ダン・アッカーマン著、小林啓倫訳(2017年/白楊社)
1『路(ルウ)』吉田修一(2012年/文藝春秋)


