Палата №6,Скучная история
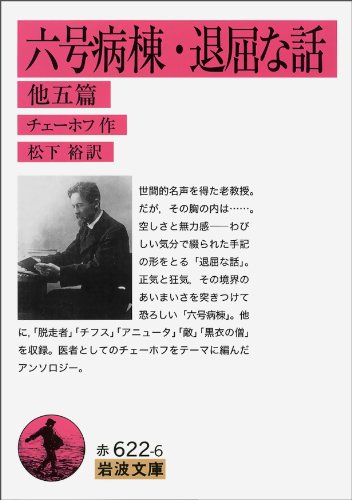
5年ほど前に初めてチェーホフの代表的戯曲、4大悲劇の2篇『桜の園』や『三人姉妹』を読んだところ、何とも曰く言い難い読後感が残った。
理解はできる、心に刺さってくるものもある、が、ではこの作品のどこがどのように自分の琴線を刺戟してきたのか、いくら考えてもよくわからない。
そういうもどかしさを何度読み返しても解消できず、それではと4大悲劇の残る2篇『かもめ』や『ワーニャ伯父さん』を読んでみても印象は変わらない。
とりわけ『かもめ』の象徴性や幕切れの酷薄さにはチェーホフ作品で一番の衝撃を感じたため、この作家はおれみたいな怠け者にもきちんと理解できるまで、様々な作品をしっかり読み込む必要がある、と考えた。
なお、この場合の「理解」とはアカデミックな意味での学習や研究による修得ではなく、あくまで一物書きとしてのカンで作品のキモをつかむことを指す。
が、戯曲はやはり舞台で演じられた劇を見なければ、そういう核心に辿り着くのは難しいかもしれない。
そこで、チェーホフのもう一つの側面、短篇小説の名手であることに着目した(というか、そうするしかなかった)。
何冊か読んだ中で、最もピンときた、これならおれでもわかる、とようやく思えて、それと同時に新たな衝撃を受けたのがこの短篇集である。
目次に沿って書くと、まず『敵』に慄然とさせられた。
ロシア僻地の郡会医(地方公共団体の診療医)キリーロフが6歳の息子をジフテリアで亡くし、悲嘆に暮れていたその夜、地元の村からアボーギンという男が突然訪ねてきて、妻が重病だ、すぐに我が家へ来てください、と訴える。
散々逡巡し、アボーギンと口論を重ねた末、キリーロフが仕方なくアボーギンの家に行ってみると、妻の姿がない。
妻は愛人の男と出ていくため、病気と偽ってアボーギンをキリーロフの元へ行かせたとわかり、呆れたキリーロフと絶望したアボーギンはさらに激しい罵り合いを繰り広げる。
疲れ果てたアボーギンの家を出たキリーロフの胸の内を、チェーホフはこう描写する。
息子を亡くした悲しみはいずれ癒えても、アボーギンに対する憎悪の感情は一生キリーロフの心中に巣喰い、彼はそれを墓場まで持っていくことになるだろう(大意)、と。
これほど人間の深層心理を文学的表現として的確に、しかも冷徹に綴った文章はほかに例を見ない。
他人から見ればつまらない恨みつらみが深い傷跡となって残り、年老いてもなお自ら古傷をえぐっては自分で自分を何度も傷つけてしまう人間の業が、容赦なく描き出されている。
次の『黒衣の僧』の主人公は、チェーホフの分身と思しき医学博士アンドレイ・ワシーリイチ・コーヴリン。
神経衰弱を患ったコーヴリンの前にはしばしば、千年も前から生き続けているという黒い修道僧が現れ、この世には「永遠の生命」が存在すると説く。
療養地でターニャという少女と知り合ったコーヴリンが、やがて彼女と愛し合うようになると、黒い修道僧は不意に目の前から姿を消した。
コーヴリンはターニャと結婚、彼女の父親の援助を受けて新たな生活を始めて、ようやくみんなが幸せになれそうだと思われた矢先、突然黒い修道僧が戻ってくる。
黒い修道僧は明らかに老いと死のメタファーなのだが、コーヴリンは結局、愛する妻や家族を捨て、黒い修道僧との生活、つまり人生の破滅を選択する。
チェーホフはコーヴリンの最期を在り来たりな悲劇としてではなく、人間が逃れようとしても逃れられない運命であるかのように綴っており、エンディングで描かれたコーヴリンの死顔が独特の余韻を残す。
表題作『六号病棟』もまた、『黒衣の僧』と同じ基本構造を持った短篇である。
主人公はアンドレイ・エフィームイチ・ラーギンは精神病院の医者で、自分が担当する六号病棟の患者イワン・ドミートリチ・グローモフの長話の相手をするのが日課だった。
グローモフが精神を病む原因となった人生の悲劇が事細かに語られ、彼の回想に相槌を打つラーギンが、内心ではグローモフを狂人とは思っていないことがわかってくる。
いったい正気と狂気を区別するものは何か、実は狂人こそが正常で、自分でまともだと思い込んでいる人間のほうこそ狂っているのではないか。
読み進めながらそんなことを考えているうち、同僚の医者の関係に嵌ったラーギンは、グローモフと同様に精神を病んでいると診断され、六号病棟に軟禁されてしまう。
患者用の寝間着を着せられ、中庭の散歩すら許されず、グローモフとともに病室で死を待つしかなくなったラーギンは、黒い修道僧とともに死ぬしかなくなったコーヴリンそっくりだ。
巻末の『退屈な話』は短篇というより中篇で、老教授の死を目前にした随想というスタイルが取られている。
自分の死を逃れられぬ運命と悟りながら、老教授は母国の社会や文学、とりわけ演劇界の状況について批判的な言葉を並べ立てないではいられない。
そうした文明批評の数々が、19世紀のロシアで書かれたにもかかわらず、21世紀の日本においても面白く、刺戟的で、強い説得力を持っているように感じられる。
本作を書き上げたとき、チェーホフはまだ39歳という若さだったが、すでに長く肺結核を病み、44歳で没するまであと5年と迫っていた。
(発行:岩波書店 岩波文庫 翻訳:松下裕 第1刷:2009年11月13日 第4刷:2016年10月25日 定価:900円=税別
原語版初出:『六号病棟』1892年、『退屈な話』1889年)
2018読書目録
6『最強軍団の崩壊』阿部牧郎(1980年/双葉社)
5『女子プロレスラー小畑千代 闘う女の戦後史』秋山訓子(2017年/岩波書店)
4『白鵬伝』朝田武蔵(2018年/文藝春秋)
3『ザナック/ハリウッド最後のタイクーン』レナード・モズレー著、金井美南子訳(1986年/早川書房)
2『テトリス・エフェクト 世界を惑わせたゲーム』ダン・アッカーマン著、小林啓倫訳(2017年/白楊社)
1『路(ルウ)』吉田修一(2012年/文藝春秋)


