Zunuck:The Rise and Fall of Hollywood’s Last Tycoon
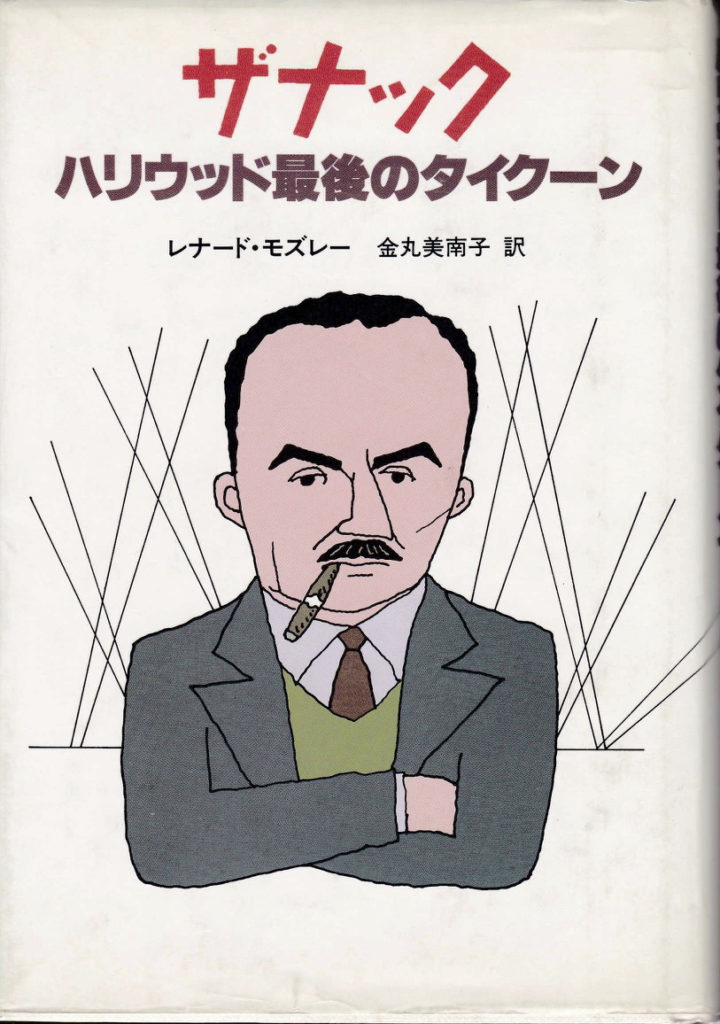
ハリウッドではいま、大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインのスキャンダルに端を発したセクハラ撲滅運動が大変な盛り上がりを見せている。
しかし、本書の主人公、ラスト・タイクーン(大君)と呼ばれたダリル・F・ザナックの前では、ワインスタインも裸足で逃げ出すかもしれない。
本書のオープニングは1930年代初頭、著者レナード・モズレーがジーン・ハーロウ主演映画の撮影現場を訪ね、初めてザナックと会った場面から始まる。
ザナックほどの大物であれば、インタビューに応じるときは紳士のはずだ、お色気女優のハーロウも淑女として振る舞ってくれるはずだ、とモズレーは直前まで思っていた。
しかし、モズレーの前に現れたザナックは乗馬用鞭の柄でハーロウの尻をつつき、卑猥な言葉を浴びせ、ハーロウもいやらしい言葉で答えると、ふたりしてゲラゲラ笑いあっていた。
当時、セクハラという言葉はまだなく、ハリウッド自体が風紀など無きに等しい街だったのだ。
女優志願で、少しでも見込みのある容姿をしている女(ほとんどは少女)がハリウッドにやってきたら、たちまちザナックのようなプロデューサーに下着に手を伸ばされた、と、この本には書いてある。
わけても、ザナックのセクハラ&性豪伝説は凄まじい。
ザナックが20世紀フォックスの撮影所長を務め、事実上この会社を支配していたころ、毎日午後4時になると女優や女優の卵がザナックの部屋に呼ばれていた。
それからザナックが相手の女性をこっそり裏口から帰すまでの30分間、撮影所ではすべての仕事がストップするのだ。
こういう白昼堂々、公私混同のセクハラ兼不倫が毎日続いていた上、ザナックは滅多に同じ女優を部屋に呼ばず、2度以上連れ込んだら何か役を与えて映画に出演させていたという。
これだけでもすごいが、ザナックが20世紀フォックスに移籍する前、ワーナー・ブラザースの製作部長を務めていたころのエピソードにはもっとあきれる。
ワーナーの創始者ジャック・ワーナーは、新しい企画書や脚本の梗概が持ち込まれると、水洗トイレの便座に腰掛け、大便をしながら読むのが常だった。
まだ年齢的には若造に過ぎなかったザナックは、ワーナーの忠実なしもべとして、ワーナーが文書を読みながらクソをしている間、流すためのチェーンに手をかけて立ったまま、じっと待っていたというのだ。
これはもう、現代のセクハラやパワハラ、ブラック企業の域をはるかに超えている。
ザナックは映画界でのし上がるため、自分を取り立ててくれる権力者の前ではいくらでも這いつくばり、抱けると見た女は片っ端から抱いては捨てた。
などと書くと、本書に対してゴシップがいっぱいの暴露本のような印象を持たれるかもしれない。
が、本書の白眉は、そうしたザナックのネガティヴな一面をきっちり記した上で、映画人としての才覚と業績をダイナミックに描いているところにある。
ザナックは当たる題材を見抜くセンス、凡作を傑作に生まれ変わらせる編集の手腕にかけては天才で、この古き佳き時代の映画の申し子だった。
とくに初のトーキー映画『ジャズ・シンガー』(1927年)、ヘンリー・フォンダを大スターに押し上げた『怒りの葡萄』(1940年)などは、監督や主演のスター以上に、ザナックのプロデュース能力なしには世に出なかっただろう。
さらに、ザナックが数億ドルもの私財を投じたのみならず、借金までして製作した『史上最大の作戦』(1962年)の製作秘話が面白い。
あの映画史上燦然と輝く戦争映画の傑作は、追い詰められたラスト・タイクーンが起死回生をかけた映画人生最後にして最大のホームランだったのだ。
著者はザナックの旧知の映画批評家であり、ザナックが死ぬまで格別昵懇の付き合いを続け、本人はもちろん、夫人のヴァージニア、息子で大プロデューサーとなったリチャードにも綿密な取材を行っている。
とりわけ、リチャードへの嫉妬に駆られたザナックが息子を20世紀フォックスの社長の座から追い落とし、撮影所からも出入り禁止にしてしまうくだりには驚かされた。
これだけ酷い目に遭わされながら、リチャードが父ザナックについて語る言葉はあくまで愛情と尊敬の念に満ちており、それがこの本の読後感を爽やかなものにしている。
ちなみに、ザナックもリチャードも、ともに77歳で亡くなっているのは何かの因縁だろうか。
これまでに様々な映画人の評伝を読んできたが、読み応えは間違いなくトップクラス。
早く現代のハリウッドで映画化してもらいたい。
(発行:早川書房 翻訳:金丸美南子 初版:1986年10月31日 定価:2600円=税別/絶版)
2018読書目録
2『テトリス・エフェクト 世界を惑わせたゲーム』ダン・アッカーマン著、小林啓倫訳(2017年/白楊社)
1『路(ルウ)』吉田修一(2012年/文藝春秋)


